ジョナサン・リテルの「慈しみの女神たち」を読み終えました [本を読んでいる]
先週の土曜日の夜、自室でジョナサン・リテル(Jonathan Littell, 1967年~ )の「慈しみの女神たち」を読み終えました。7月17日から8月25日まで、途中約一週間の家族旅行によるブランクがあったものの、平日、朝の通勤電車の中で読み続け、なんとかこの上下巻で約900頁、二段組みにびっしりと活字で埋まった重たい本を読了したこととなります。
この、SS将校アウエ博士の独白で語られる物語は、その第二次世界大戦におけるドイツ軍の行動を、ユダヤ人虐殺に焦点を当てながら、実際の歴史に即した形で、(SS将校の立場から)非常に詳しく、また非常なリアリティをもって描ききった部分と、逆に、西洋における近代的自我、インテリゲンチャの一典型としての主人公の、とても幻想的かつ矛盾と倒錯に満ちた半生とが複雑に絡み合う体裁を取りながら、人間という存在の本質を問う小説であると思います。
ユダヤ人絶滅の任務と正義を負わされた兵士たち。極限と混沌のさなか、しかし誰が彼らを殺さずにいられたか―小説という虚構によってこそ見出される、ナチス・ドイツのかつてない真実。フランス二大文学賞受賞、世界各国で話題沸騰の問題作ついに日本上陸。(「BOOKデータベース」からの引用)
ドイツ軍の記述が、非常に綿密かつ詳細にわたるもので、読者があたかも自分もドイツ将校として、一緒にいるかのような気にさせてくれる(それは悪夢としか言いようもないものですが)ものであるのに対し、主人公の半生については近親相姦と隔離、母性憎悪(偏愛)に基づく、同性愛への傾斜、殺人といった、汚辱にまみれたものでありながら、ある意味、非常に幻想的としか言いようのない、謎に満ちた神話的な物語として語られていきます。それが、相互に絡まり合って、最後の最後に一つの結び、それも父殺し、兄殺しにも似た悪の極致の形態を得る、その見事さに、私は純粋に、文学的な感動を得ました。それは決して後味の良いものではありませんが、人間というものの負の面を暴き、描ききっているところに、私は、この小説の最大の魅力を感じたのです。
約一ヶ月超の読書体験でしたが、今は頭をからっぽにして、暫くの間、この小説の余韻を味わっていたいと思っています。今、私はこの小説について考える必要、それはすなわち、この小説に解釈を与える必要があるのです。決して誰にでも勧められる小説ではないかと思いますが、読む価値は多分、ここ、何年かに出た本の中ではひときわ高い、そういう本だと思います。
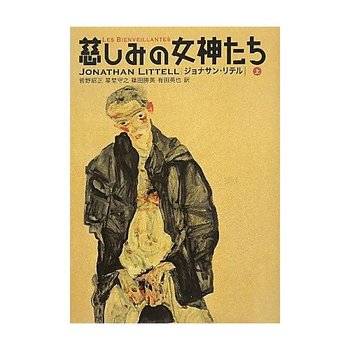
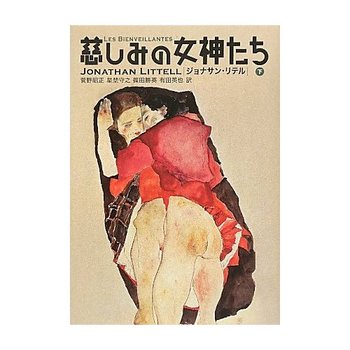
写真はジョナサン・リテルの「慈しみの女神たち(上・下)」(集英社)。Wikipediaによると、作者はユダヤ系アメリカ人で、父親はアメリカのスパイ小説作家ロバート・リテルとのこと。(この小説はフランス語で書かれています)この小説で彼は2006年のゴンクール賞とアカデミーフランセーズ賞を受賞しました。
この、SS将校アウエ博士の独白で語られる物語は、その第二次世界大戦におけるドイツ軍の行動を、ユダヤ人虐殺に焦点を当てながら、実際の歴史に即した形で、(SS将校の立場から)非常に詳しく、また非常なリアリティをもって描ききった部分と、逆に、西洋における近代的自我、インテリゲンチャの一典型としての主人公の、とても幻想的かつ矛盾と倒錯に満ちた半生とが複雑に絡み合う体裁を取りながら、人間という存在の本質を問う小説であると思います。
ユダヤ人絶滅の任務と正義を負わされた兵士たち。極限と混沌のさなか、しかし誰が彼らを殺さずにいられたか―小説という虚構によってこそ見出される、ナチス・ドイツのかつてない真実。フランス二大文学賞受賞、世界各国で話題沸騰の問題作ついに日本上陸。(「BOOKデータベース」からの引用)
ドイツ軍の記述が、非常に綿密かつ詳細にわたるもので、読者があたかも自分もドイツ将校として、一緒にいるかのような気にさせてくれる(それは悪夢としか言いようもないものですが)ものであるのに対し、主人公の半生については近親相姦と隔離、母性憎悪(偏愛)に基づく、同性愛への傾斜、殺人といった、汚辱にまみれたものでありながら、ある意味、非常に幻想的としか言いようのない、謎に満ちた神話的な物語として語られていきます。それが、相互に絡まり合って、最後の最後に一つの結び、それも父殺し、兄殺しにも似た悪の極致の形態を得る、その見事さに、私は純粋に、文学的な感動を得ました。それは決して後味の良いものではありませんが、人間というものの負の面を暴き、描ききっているところに、私は、この小説の最大の魅力を感じたのです。
約一ヶ月超の読書体験でしたが、今は頭をからっぽにして、暫くの間、この小説の余韻を味わっていたいと思っています。今、私はこの小説について考える必要、それはすなわち、この小説に解釈を与える必要があるのです。決して誰にでも勧められる小説ではないかと思いますが、読む価値は多分、ここ、何年かに出た本の中ではひときわ高い、そういう本だと思います。
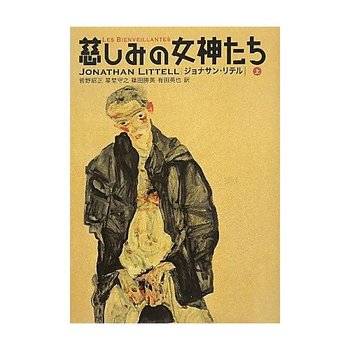
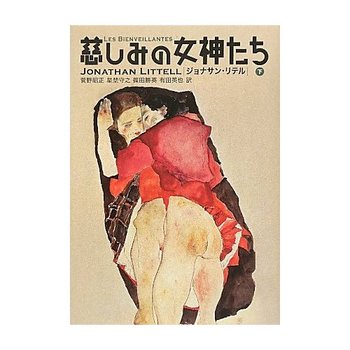
写真はジョナサン・リテルの「慈しみの女神たち(上・下)」(集英社)。Wikipediaによると、作者はユダヤ系アメリカ人で、父親はアメリカのスパイ小説作家ロバート・リテルとのこと。(この小説はフランス語で書かれています)この小説で彼は2006年のゴンクール賞とアカデミーフランセーズ賞を受賞しました。



